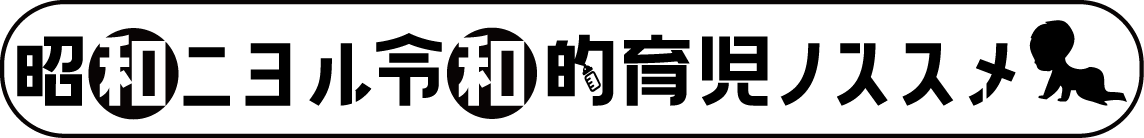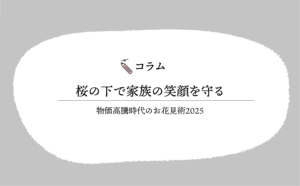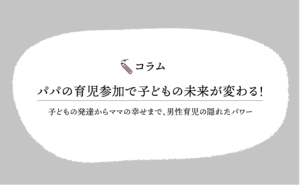父親の産後うつ - 知られざる育児の危機と家族を守るための対策
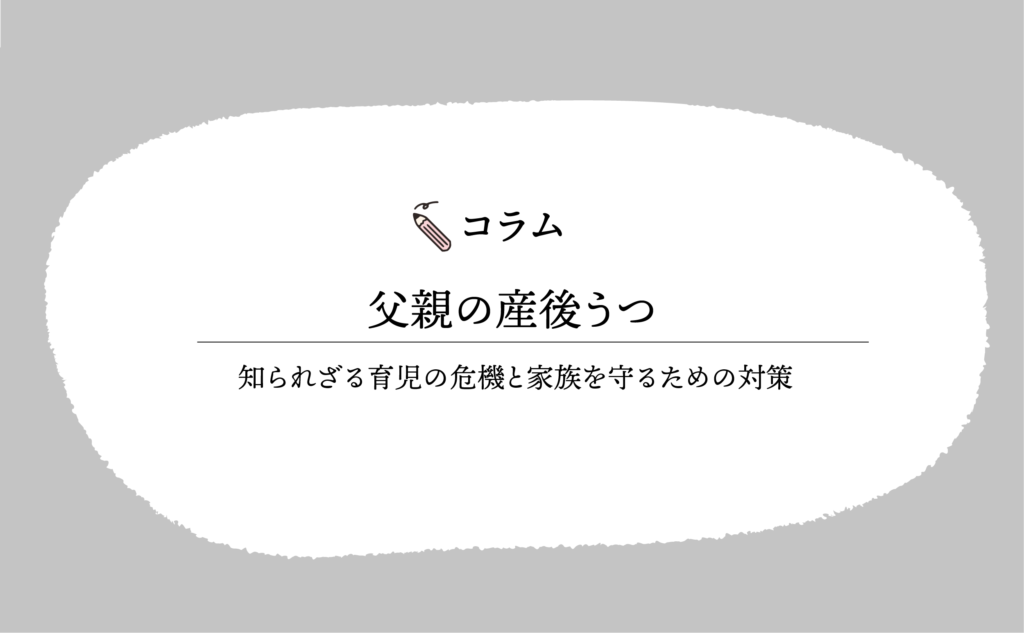
「子どもが生まれて嬉しいはずなのに、なぜか気分が落ち込む…」「仕事に集中できず、家に帰っても育児に自信が持てない…」
こんな悩みを抱える父親が、実は珍しくありません。母親の産後うつは広く認知されていますが、父親も同様に産後うつに悩むことがあるという事実は、まだ十分に知られていないのが現状です。
この記事では、父親の産後うつの実態と支援策について詳しく解説します。育児に奮闘する父親やそのパートナー、そして支援者の方々にぜひ最後までお読みください。
父親の産後うつの実態
意外に高い発症率
驚くべきことに、父親の産後うつの発症率は全体の約10〜11%と、母親の産後うつとほぼ同水準です。日本で実施された調査によると、産後1年間でうつのリスクありと判定された父親は11.0%であり、母親の10.8%とほぼ同じ水準でした。さらに注目すべきは、夫婦同時期にリスクありと判定された世帯が3.4%に達していることです。
産後1カ月が発症しやすい時期とされており、父親としてのプレッシャーやパートナーの出産という環境の変化により、精神的に不安定な状態になることがあります。
見過ごされがちな症状
父親の産後うつの症状には、以下のようなものがあります:
- 活字が頭に入ってこない
- 疲労感やイライラ感が続く
- 集中力が低下して仕事の成果が落ちる
- 家族と過ごしていても楽しいと感じられない
- 自分が家族に役立っていないと感じる
これらの症状が続く場合、産後うつの可能性を考える必要があります。
父親の産後うつを引き起こす要因
生活環境の変化
子どもの誕生は、父親の生活にも大きな変化をもたらします。夜泣きや育児などを含め生活リズムが変わり、十分な睡眠や息を落ち着ける時間が取れず、心身ともに疲弊しやすくなります。
仕事と育児の両立
父親が産後うつに陥るパターンの一つに、育児と仕事の両立困難があります。育児と仕事を両立しようと頑張るものの、仕事の負担が減らない中で育児を担うため両立が困難になり、メンタルヘルス不調を起こしてしまうことがあります。
「有害な男らしさ」の影響
「有害な男らしさ」とは、「男性だからかくあるべき」といった固定観念で、日本人の男性には多く見られます。「子供が産まれたから、仕事をより頑張らなくては」と意気込み、仕事を増やしたり、転職をしたり、自ら多重負荷を課して追い込まれてしまうケースがあります。
社会との隔絶
終わりが見えない育児に疲弊すると同時に、仕事から取り残される不安感などが重なり、これらを相談できるつながりや外部支援がないことで追い込まれるパターンもあります。
父親の産後うつが家族に与える影響
父親の産後うつは、本人だけの問題ではありません。放置すると、家族全体に連鎖的な影響を及ぼし、負の循環を生み出してしまいます。
わたしの友人は、第一子誕生後に産後うつの症状が出始めましたが、「男なのに弱音を吐けない」と我慢していました。その結果、家族全体が苦しむことになったと後悔していました。
負の連鎖が生み出す家族の危機
父親の産後うつが引き起こす影響は、まるで糸で繋がったドミノのように、一つが倒れると次々と連鎖していきます。
まず、父親自身は集中力や思考力が低下し、仕事のパフォーマンスが落ちます。これにより自己評価が下がり、さらにうつ症状が悪化するという悪循環に陥ります。「最近、仕事でミスが増えたな…」と感じ始めたら要注意です。
この状態が続くと、赤ちゃんとの関係にも影響が出始めます。父親が情緒不安定になると、赤ちゃんとの健全な愛着形成が難しくなります。赤ちゃんは親の感情に敏感で、父親の不安やイライラを感じ取り、情緒や社会性の発達に影響が出ることもあります。
さらに、父親が育児から遠ざかることで、母親への負担が増大します。「つまが一人で育児を頑張っているのに、自分は何もできない…」という罪悪感が父親の心を更に苦しめ、うつ症状を悪化させるという悪循環も生まれます。
そして最終的に、夫婦関係にも亀裂が入りやすくなります。コミュニケーション不足から誤解が生じ、お互いを思いやる余裕がなくなり、家庭内の緊張感が高まります。「最近、つまと話す時間がほとんどないな…」と感じたら、すでに危険信号かもしれません。
連鎖を断ち切るために
この負の連鎖を断ち切るには、早期発見と適切なサポートが不可欠です。父親の変化に気づいたら、パートナーや周囲の人は「大丈夫?」と声をかけ、話を聞く姿勢を持ちましょう。
つまは最近、「パパの調子が悪いと、家族全員に影響するから、無理しないで早めに相談してね」と言ってくれました。確かに、一人で抱え込むより、家族で支え合うことで、この連鎖を断ち切ることができるのです。
父親を支援するために
家族ができること
しんどい時にしんどいと言える関係性を築くことが大切です。特に男性は弱音を吐きづらい傾向がありますが、パートナーが「何でも話してね」という姿勢を見せることで、心を開きやすくなります。
わたしの場合、つまが「最近どう?疲れてない?」と何気なく聞いてくれたことで、少しずつ本音を話せるようになりました。些細な変化に気づき、声をかけ合うことが大切です。
そして、これは双方向の配慮が必要です。パートナーの変化にも敏感になり、同じように声をかけることで、互いに気遣い合う関係が築けます。このような関係性があれば、問題が大きくなる前に早めの対処ができ、より健全な家族関係を維持できるでしょう。
企業・職場ができること
企業は、男性の育休取得推進に向けて取り組んでいますが、今後は「育休前後」にも目を向けていただきたいです。妊婦健診の同伴に配慮することや、「育休が明けたら以前通りに仕事」ではなく、「育児と仕事の両立のために配慮する」という観点が重要です。
育児休業法でも、育児中の従業員は、時間外勤務の制限などを請求できることが明記されています。また、産業医がいる企業では、育児や仕事との両立など、何か不安なことや分からないことがあったら、産業医にいつでも相談できるという事を、企業から発信していくことも重要です。
もし現在の職場が全く理解を示さない場合は、働き方や職場を見直すことも一つの選択肢です。子どもの誕生を機に、自分のキャリアや働き方を見つめ直す良い機会かもしれません。
社会・行政ができること
行政は、父親に出産や育児の情報が行き渡るよう、地域の父親学級を増やすことなどが必要です。母親教室や妊婦健診など母親に向けた支援は手厚いですが、父親には十分な支援も、知識も届いていません。
2025年1月には、日本初となる自治体向け父親支援マニュアルが公開されました。このマニュアルは「父親の産後うつ」や孤立を防ぎ、幸せな子育て期の実現を目指しています。
新しい時代の父親像へ
育児・介護休業法の改正など、男性の育児参画が進む今、「父親のあり方」も変化しています。昭和時代の「頑固親父」から2000年代の「イクメン」へと移り変わってきました。
「イクメン」という言葉は男性の育児参加を促進する効果がありましたが、「完璧に育児をこなさなければならない」というプレッシャーも生み出していました。
これからは理想の父親像を追い求めるのではなく、多様な父親のあり方を認め合い、それぞれの形で育児に関わることを尊重する社会が必要です。父親への適切な支援は、父親自身の健康だけでなく、子どもの健全な発達や母親の負担軽減にもつながり、家族全体の幸せに直結します。
長い間、「男性は弱音を吐くべきではない」という価値観がありましたが、その時代は終わりつつあります。しんどい時には弱音を吐いていい。「男のくせに」という言葉に縛られる必要はないのです。
一人で抱え込まず、パートナーや周囲に相談することが、あなた自身と大切な家族を守ることにつながります。多様な父親像を認め合う社会こそが、すべての家族の幸せを支える基盤になるのです。