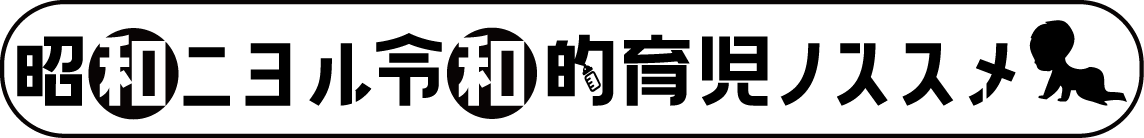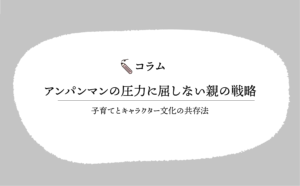「子どもは育てたくない」52%の衝撃 - 日本の若者が抱える本音と未来への不安
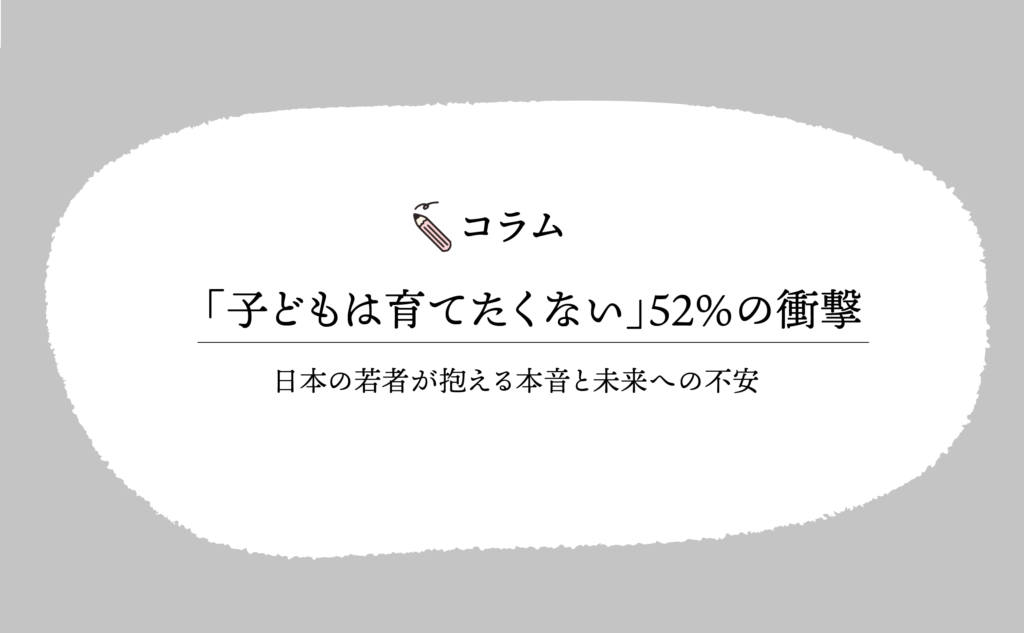
子育て中のあなた、最近のニュースを見て「この国で子育てしていて大丈夫だろうか」と不安になることはありませんか?特に「子どもは育てたくない」と考える若者が52%にも達したという衝撃的な調査結果を目にして、胸が締め付けられる思いをしたのではないでしょうか。
実は私も子どもが生まれてから、ニュースの見方が変わりました。「この子が大人になる頃の日本はどうなっているんだろう」と考えずにはいられなくなったんです。特に少子化に関するニュースを見るたびに、親として何ができるのか考えてしまいます。
この記事では、話題になった「子どもは育てたくない若者52%」の調査結果を詳しく解説し、その背景にある若者の本音と、私たち親世代ができることについて考えていきます。子育て中のパパ・ママはもちろん、将来子どもを持つかどうか迷っている方にもぜひ最後まで読んでいただきたいと思います。
衝撃の調査結果:若者の半数以上が「子どもは欲しくない」
日本大学の末富芳教授率いる研究チームが2025年2月に実施した全国調査によると、15〜39歳の若者の52%が「子どもがおらず、育てたくない」と回答しました。この調査は全国の若者4,000人を対象にオンラインで行われたものです。
調査結果の詳細
- 子どもがいると回答:14.9%
- 子どもはいないが欲しいと回答:32.1%
- 子どもがおらず、欲しくないと回答:52%
特に注目すべきは、年収299万円未満、または世帯年収399万円未満の回答者では、子どもを欲しくないと答えた割合が約60%に上昇している点です。

この調査結果見たときどう思った?

正直、数字だけ見るとショックだけど、若い世代の気持ちも分かるよね。特に経済的な理由が大きいみたい
実際、ロート製薬が実施した18〜29歳の未婚男女400人を対象とした別の調査でも、「将来子どもを持ちたくない」と回答した人の割合が55.2%に達し、初めて半数を超えました。男性は約60%、女性は51.1%が子どもを望んでいないという結果でした。
若者が「子どもを持ちたくない」本当の理由
調査結果から見えてきた、若者が子どもを持ちたくない主な理由は以下の通りです:
経済的懸念
子育てにかかる費用、特に教育費の負担が大きいと感じている若者が多いです。年収が低い層ほど「子どもは欲しくない」と回答する傾向が強いことからも、経済的な不安が大きな要因であることが分かります。
仕事と育児の両立の難しさ

わたしの職場でも、はっきり言って子育てと仕事の両立は無理でしょう?って思うほど頑張っている人がたくさんいるんだ。子供のために働いているのに、結局その子供との時間は限られてしまう。そんな姿を見て、若い人たちが『自分もそうなりたい』とは思わないよね
長時間労働や柔軟性に欠ける職場環境が、若者の子育てへの意欲を削いでいます。
家事・育児の負担とジェンダー格差
特に女性が感じる負担の大きさは深刻です。共働きが当たり前になった現代でも、家事や育児の負担は女性に偏りがちです。
将来への不安
日本の経済状況や社会保障制度に対する不安感も大きな要因です。「この先の日本で子どもを育てていけるのか」という漠然とした不安が、若者の背中を押せない状況を作っています。
若者が求める少子化対策とは
同調査では、若者が少子化対策として必要だと考える施策も明らかになりました:
働き方に関する要望
- ワークライフバランスの改善:78.2%
- リモートワークなどの柔軟な働き方:77.8%
- 育児休暇を取りやすくすること:76.5%
経済的支援策への期待
- 若者への経済的支援:61.7%
- 公共料金の割引や免除:61.4%
- 家賃補助:57.4%
- パートタイムや契約社員への職業訓練・就職準備の補助:55.5%
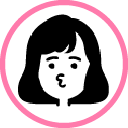
この結果を見ると、お金の支援よりも働き方の改革を求める声のほうが多いのね

そうなんだよね。もちろんお金の問題も大きいけど、時間や生活の質を重視する傾向が強いみたい。子育てしながらも自分の人生を大切にしたいという思いが表れているんじゃないかな
理想と現実のギャップ
東京商工会議所が実施した18〜34歳の若者2,198人を対象とした調査では、興味深い結果が出ています。理想の子ども数については70%以上が複数の子どもを望んでいるものの、現実的に持てる子どもの数については大きく変わり、子どもを持てないと考える人が20.4%、1人だけと考える人が35.3%という結果でした。
つまり、本当は子どもが欲しいと思っている若者も多いのですが、様々な要因から「育てられない」と感じ、結果的に「育てたくない」という感情になっているケースが多いと推測できます。
著名人の反応
「子どもは育てたくない」若者が52%という調査結果に対して、著名人からも反応がありました。
つるの剛士の反応
タレントのつるの剛士(49歳)は2025年3月22日までにXを更新し、この調査結果について自身の見解を述べました。つるのは「“子どもは育てたくない”のではなく”育てられない”が正しいのでは?」と指摘しました。
その理由として「若い世代の収入が増えなければ結婚や子育てに夢なんかもてるわけがない」と経済的要因を挙げ、「配るなら最初から取らない(減税)対策を進めるべきでは…と五児父の切実な想い」とコメントしました。
つるのの投稿には「賛成です!」「配るなら最初から取らないって考えは、私も、それがベストだと思います」「わかります」など多くの共感の声が寄せられています。
成田修造の反応
一方、起業家の成田修造氏(35歳)は2025年3月23日にXを更新し、同じ調査結果に対して異なる視点からコメントしました。
成田氏は「普通の人こそ、子供持つといいと思うんだけど、みんなバカやなー 子供わちゃわちゃすぎてめっちゃ生きてる感出るし 究極の暇つぶしになるのにな みんななんのために生きてるのw」と投げかけました。
さらに「お金がないから。遊びたいから。仕事したいから。そんな理由で子供持たないとか馬鹿だろ」とし、「まあ、実際には多くの人が大して稼いでもいないだろうが、そのはした金を何のために稼いでいるのか?自分が80歳90歳まで老いぼれていくために稼いでいるのか?」と厳しい意見を述べました。
親世代にできること、社会に求められる変化
「子どもは育てたくない」と考える若者が増える中、私たち親世代にできることは何でしょうか。
子育ての喜びを伝える
子育ての大変さばかりが強調される風潮がありますが、子どもと過ごす時間の素晴らしさや、成長を見守る喜びも伝えていくことが大切です。
子育てしやすい社会への声を上げる
私たち自身が子育てしやすい社会を求めて声を上げることで、次の世代の環境を少しでも良くすることができます。職場での育児理解を促進したり、地域の子育て支援を活用・応援したりすることも重要です。
子育て世代向けの商品・サービスを選ぶ
子育て支援に積極的な企業の商品やサービスを意識的に選ぶことで、社会全体の子育て支援の機運を高めることができます。例えば、育児休業制度が充実している企業の商品を選んだり、子連れOKの飲食店を利用したりすることも一つの方法です。
まとめ:子どもの未来のために、今できること
「子どもは育てたくない」と考える若者が52%という調査結果は、日本社会の抱える課題を浮き彫りにしています。
本当の幸せとは何かを社会全体で見つめ直し、その価値観を社会の仕組みに反映させることが重要です。子育てや家族との時間を大切にでき、経済的不安のない社会を目指すことで、自然と子どもを持ちたいと思う人も増えるでしょう。
この問題の解決には、一人ひとりが関心を持ち、声を上げることが不可欠です。単に結果を嘆くのではなく、背景にある社会の歪みを正していく必要があります。「どんな社会に生きたいか」を考え、行動することで、少しずつ変化が生まれます。
子育て中のパパ・ママの皆さん、日々の忙しさの中で不安を感じることもあるかもしれませんが、子どもたちの笑顔のために、一緒に未来を変えていきましょう。あなたの小さな行動が、次の世代の希望につながるかもしれません。