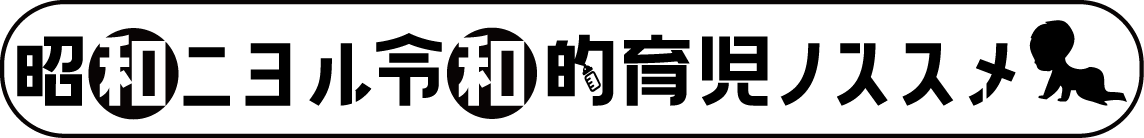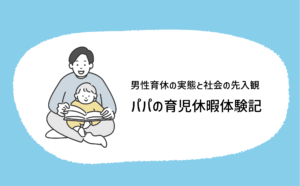育休は”休み”じゃない!40代パパが見つけた料理との出会いと家族時間の充実法
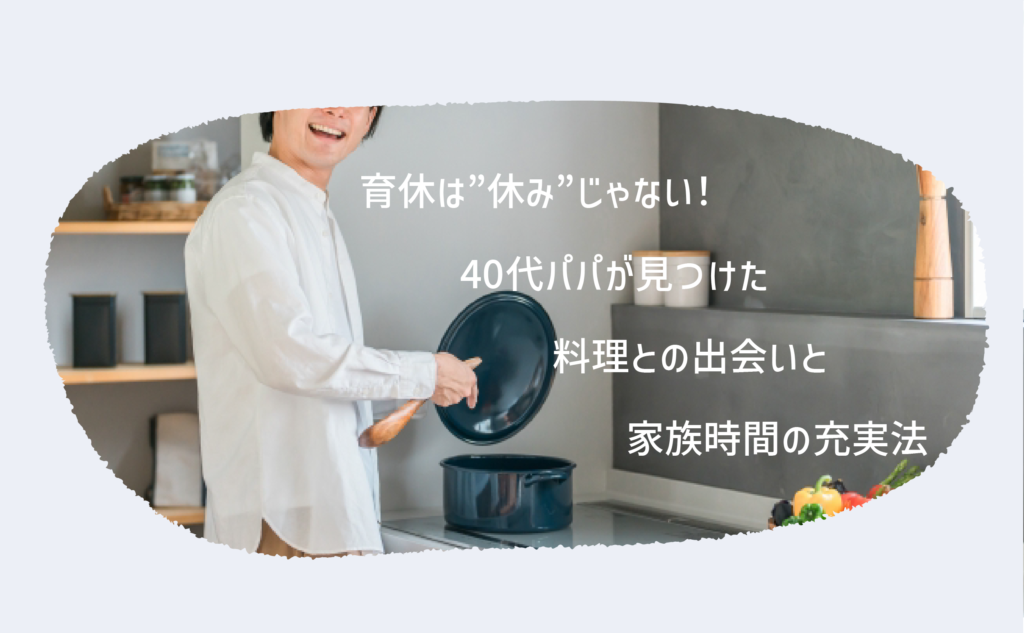
毎日「今日は何をしよう?」と迷いながら、育休中なのに充実感が得られないと感じていませんか?
私も育休に入ってしばらくの間、この時間をどう過ごすべきか手探り状態でした。
男性の育休取得がまだ一般的でない職場の中、長期間の育休を取得したからには、この貴重な時間を有意義に使いたいという思いがありました。
授乳以外の育児はすべてチャレンジしようと決め、積極的に家事・育児に関わる中で、意外なことに「料理」との出会いが育休生活を一変させたんです。
家族の「おいしい!」という言葉に喜びを見出し、単なる家事だったものが趣味へと変わっていきました。
この記事では、育休の”質”を高める秘訣として、料理を通じた家事・育児シェアの工夫をご紹介します。
特に、「料理なんて面倒…」と思っている育休パパや、パートナーの家事参加に悩むママにとって役立つ内容になっています。
育休を単なる「休み」ではなく、家族との特別な時間、自分自身の成長期間に変える方法を知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
- 育休男性の家事参加の現状
- 料理という入口:育休男性が最初に挑戦しやすい家事
- 家事参加がもたらす4つの効果
- 家事シェアの具体的実践法
- 育休後も続く家事参加の習慣化
- まとめ:家庭と社会を変える男性の家事参加
育休男性の家事参加の現状
育休という言葉、実はかなり誤解を招きやすいものです。
「休暇」という響きが社会的にも家庭的にも「休んでいる」という印象を与えてしまっています。でも実際は違います。
育休の本質は「休み」ではなく
- 家族との特別な時間
- 人間的な価値を見出す期間
- 新たな価値観を得るチャンス
総務省の調査によると、6歳未満の子どもを持つ世帯において、夫の家事時間は2001年の7分から2021年には30分へと4.2倍に増加しました。
しかし、妻の家事時間(2時間58分)と比べるとまだ大きな差があります。
日本は国際的に見ても、男性の家事・育児参加が特に少ない国です
6歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児時間を比較すると、日本では妻の負担割合が約85%を占め、夫の負担割合はわずか15%程度。女性と男性の差は5倍以上にのぼります。
一方、アメリカやヨーロッパの国々では、夫の負担割合は約30~40%に達し、その差は2~3倍程度です。
このような状況の中で、男性の育休取得は家事参加を促進する重要な機会となります。
しかし、ただ漠然と過ごすだけでは、その機会を活かしきれません。
1年間の育休生活を通して気づいたのは、基本的な一日のルーティンが確立すると、心に余裕が生まれるということ。
仕事と同じで、育休という「仕事」も見通しが立つとペース配分がわかってきます。
単調に感じるかもしれませんが、この「予測可能な流れ」こそが、新しいことに挑戦する余裕を生み出し、育休の質を高めるきっかけになるんです。
料理という入口:育休男性が最初に挑戦しやすい家事
育休パパにとって料理は避けては通れない家事の一つです。
「料理ができないから…」と言っていては、家庭での居場所が見つかりません。
でも安心してください。難しい料理をマスターする必要はないんです。
最初から完璧を目指す必要はありません。まずは失敗してもいいから、「やってみよう」という姿勢を見せることが大切です。
初心者パパのための料理スタート法
今から料理を始める人には、YouTube一択をおすすめします。
料理本を開きながらするより、映像で見る方が圧倒的に伝わるものが多いです。
初心者におすすめのアプローチ
- まずは気に入った料理動画を見るだけでOK
- 「これなら自分でもできそう」と思える動画を選ぶ
- 一流シェフの超絶技巧動画は避ける
- 「りゅうじのバズレシピ」「Koh Kentetsu Kitchen」など初心者向けコンテンツを活用
実際、多くの男性が育休中に料理スキルを身につけることで、家事シェアがスムーズになっています。
最初は動画を見ながら忠実に再現することから始めましょう。
調味料を丁寧に量り、時間を守って作ることが大切です。
何事も上達の秘訣は「真似ること」にあります。
一定期間丁寧に料理に取り組むと、経験値が貯まりレシピへの依存度が下がります。
「この調味料がないから作れない」といった壁を乗り越えられるようになり、料理をより簡単に捉えられるようになるんです。
最初はレシピ通りに作っていても、やがて冷蔵庫にあるもので即興で作れるようになります。
これはレシピの呪縛から解放された証拠です。
家事参加がもたらす4つの効果
男性が育児・家事に積極的に参加することで、「やってあげる」から「やらなければならない」という意識の変革につながります。
そして何より、夫婦の信頼関係や子どもとの関係も良くなるのです。
夫婦関係の満足度向上
研究によれば、夫婦間の家事・育児の分担割合が同等に近づくほど、夫婦ともに満足度が高くなることが分かっています。
特に育児期においては、夫の育児参加が妻の夫婦関係満足感を高める効果があります。
出生率への好影響
ヨーロッパの調査では、男性の家事・育児負担割合が高い国ほど出生率が高い傾向が見られます。
男性の子育て負担割合が高いと、女性は「もう一人子供を産み育てたい」と思えるようになるからです。
男性自身の幸福感向上
家族と過ごす時間が幸福感に結びつくことは多くの調査で指摘されています。
カナダの研究では、平均5週間の育児休業を取得した男性は、3年後も家事・育児時間が20%増加していたことが分かっています。
短期間の育休でも、その後のライフスタイルに大きな変化をもたらすのです。
子どものジェンダー観への影響
子育てをする父親と、外で働く母親の姿を見て育った子どもは、ジェンダーニュートラルな態度を自然に学びます。
このような子どもは将来親になった時も、自然に家事・育児に参加できるようになります。
家事シェアの具体的実践法
育休を効率的に:時間管理のコツ
育休中に直面する現実——家事は終わりがなく、今日やっても明日また同じことの繰り返し。
特に料理は毎日の大きな時間とエネルギーを消費します。
私が見つけた解決策は「一日単位」ではなく「一週間単位」で考えること。
明日の献立だけを考えていると、あっという間に「また夕食何作ろう…」という悩みの無限ループに陥ります。
週単位の献立計画のメリット
冷蔵庫の食材を見渡して「今週は肉じゃが、麻婆豆腐、タンドリーチキン、サバの味噌煮」とざっくりでも計画を立てておくだけで、毎日の「今日は何作ろう問題」から解放されます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、少しずつ経験を積むことで自然とこの思考パターンが身につきます。
こうして時間の使い方にメリハリがつき、育児や自分の時間に余裕が生まれるのです。
パラレル家事のすすめ
「料理した人は洗い物をしない」——このシンプルなルールを導入するだけで、家事分担が驚くほどスムーズになります。
これが「パラレル家事」の基本で、お互いの不公平感を減らし、チームワークを高める効果があります。
同じ家事をしていても、「暗黙の了解」と「明確なルール」では結果に雲泥の差が生まれます。
このルールが習慣化すると、「言われなくても自然に動く」理想的な家事分担が実現します。
夫婦で育休を取得している場合は特に、「なんとなく」ではなく「明確に」役割分担を話し合っておくことが重要です。
責任感が生まれ、「あなたがやるべきだった」といった不満の種を減らせます。
さらに、「気づいたら先にやる」という姿勢がお互いにあれば、家事はさらにスムーズに回るようになります。
育休後も続く家事参加の習慣化
コロナ禍の影響で在宅時間が増加した男性の約6割が「積極的に家事・育児に参加するようになった」と回答しており、男性の育児時間は約3時間(コロナ前と比べて+1時間)、家事時間は約2時間(同+40分)に増加しています。
このように、環境が変われば男性の家事・育児参加は確実に増えるのです。
カナダの研究が示すように、短期間の育休でも3年後の家事・育児時間が20%増加するという結果は、育休中に身につけた家事スキルが職場復帰後も活きることを示しています。
料理の基本を覚え、家事の分担方法を確立することで、育休後も家事参加の習慣が続きやすくなります。
育休中に「やってあげる」から「やらなければならない」という意識変革が起こることで、復職後も自然と家事に参加できるようになるのです。
まとめ:家庭と社会を変える男性の家事参加
スマホを見ていると、育休中なのに何もしない夫を揶揄する漫画がタイムラインに流れてくることがあります。
せっかく社会が男性の育休取得を推進し、制度が整いつつある中で、「結局男性育休は役に立たない」という印象が強まるのは残念です。
昭和のお父さん感覚で育休に入ると、「取るだけ育休」になりかねません。
夫が育休を取って子育てがしやすくなったと実感できる家庭、家事育児に奮闘するお父さんで溢れる社会になれば、もっと素敵な未来が待っているはずです。
育休は単なる休みじゃなくて、家庭という別のフィールドでの活躍の場です。
特に40代は古い価値観と新しい家族のあり方の間で揺れることも多いですが、積極的に関わることで新しい自分に出会えるのです。
料理という入口から始まる家事参加が、家族の幸福度を高め、社会全体にも良い影響をもたらします。皆さんも育休中、ぜひ新しい自分との出会いを楽しんでください。