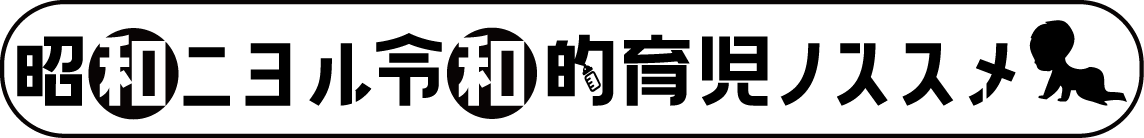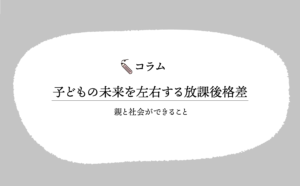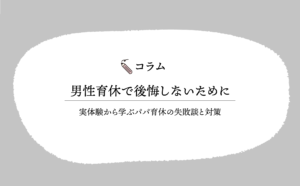「パパの歌」から考える現代のパパ像〜忌野清志郎が教えてくれた父親の在り方〜
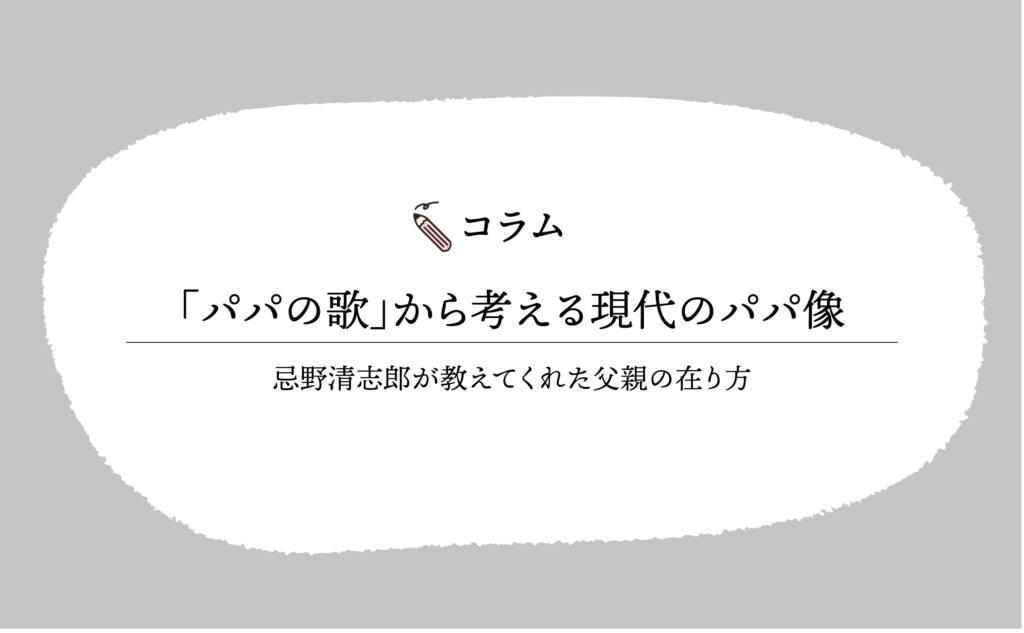
子育てに奮闘している最中、ふと耳に入ってくる昔の曲。「パパの歌が聞こえてくるよ〜」というフレーズで始まる忌野清志郎の「パパの歌」を聴いたことはありませんか?この曲が1992年にリリースされてから、パパの在り方は大きく変わりました。当時は「仕事人間」が当たり前だった父親像が、今では「育児参加」が当然となっています。
清志郎の「パパの歌」を聴き直してみると、昔のパパっぽいなと思わさせられる歌詞の中に、時代を超えた父親の愛情のあり方が見えてきます。今回は、この名曲を手がかりに、現代のパパ像について考えてみましょう。
「パパの歌」に描かれた90年代のパパ像
「パパの歌が聞こえてくるよ 遠くからパパの歌が聞こえてくるよ」
この歌詞を聴くと、なんとなく距離感のあるパパの姿が浮かんできますよね。1991年に発表されたこの曲は、RCサクセションが無期限活動休止になって以来の初のシングルでもあり、清水建設のCMソングとして使われました。
当時のパパといえば、朝早く出勤して夜遅く帰宅。子どもが起きている時間に家にいないことも珍しくありませんでした。でも、清志郎はこんな歌詞も歌っています。
「パパはいつでもそばにいるよ」
物理的な距離があっても、心は常に子どもと共にある—そんな父親の深い愛情が表現されているのです。
清志郎自身のパパとしての姿勢から学ぶこと
伝説的ロックンローラーだった清志郎は、二児の父でもありました。1988年に父親となった清志郎にとって、子どもの誕生は世界観が変わるほどの大きな出来事だったようです。
多忙なミュージシャン生活の中でも、子どもたちとの時間を大切にし、ライブや創作活動において子煩悩ぶりを発揮していました。「パパの歌」は、そんな清志郎の父親としての愛情が詰まった作品です。
清志郎は「型にはまらない父親像」を体現し、権威的な父親ではなく、子どもと対等に向き合う姿勢を大切にしていました。これは今の時代にこそ求められる父親像ではないでしょうか。
バブル崩壊から令和へ:変わりゆくパパ像
「パパの歌」から約30年。父親像は大きく変化しました。
実際に育休を取得しているわたしの肌感覚からも、平日にベビーカーを押しているお父さんの姿が珍しくありません。言葉を交わすことはありませんが、そんなお父さんたちに同志のような仲間意識を勝手に覚えています。
今では男の育児はあたりまえですが、当時は「イクメン」なんて言葉もなかった時代です。そんな時代に、子どもとの時間を何よりも大切にし、そのかわいさを表現したバンドマンは他にいなかったのではないでしょうか。
さらに、コロナ禍でテレワークが普及したことで、家庭での父親の存在感はさらに高まりました。「遠くから聞こえるパパの歌」ではなく、「そばで一緒に歌うパパ」が現代の理想像となっています。
現代のパパに求められる「しなやかな父性」
仕事も家庭も両立するのは、実際かなり大変です。でも今求められているのは、強さと優しさを併せ持つ「しなやかな父性」なのではないでしょうか。
現代社会で求められているのは、清志郎が体現していたような、権威的ではなく対等な関係性を築く父親の姿勢です。仕事と家庭の両立は依然として課題ですが、「どちらかを犠牲にする」のではなく、「どちらも大切にする」という価値観が広がっています。
清志郎とジョン・レノン:二人の父親像
海外にも、清志郎と似たようなパパがいました。ハウスハズバンド(主夫)宣言をし、丸5年も育児と家事に専念したジョン・レノンです。
自分の子どもを、清志郎は「ラッキーボーイ」、ジョン・レノンは「ビューティフルボーイ」と表現しました。二人とも、子どもへの無条件の愛と、子どもが自分の人生を歩んでいくことへの応援メッセージを込めています。
これからのパパ像:清志郎から学ぶメッセージ
多様性が尊重される現代社会において、「こうあるべき」という固定的なパパ像はもはや存在しません。それぞれの家庭に合ったパパの在り方があります。
どんな形であれ、子どもとの関係性構築が一番大事です。清志郎が歌ったように「いつでもそばにいる」という安心感を子どもに与えることが大切です。
実は「パパの歌」の1年後には「パパの手の歌」も発表されています。この曲では、子どもの目から見た「なんでもパパパっとこなす」パパの手に焦点が当てられており、次世代へと受け継がれていく父親の役割が描かれています。
清志郎が体現していた「自分らしく生きる姿勢」は、現代のパパたちにとっても大切なメッセージとなるでしょう。型にはまらず、自分らしく、そして子どもを心から愛する—そんなパパであることが、どんな時代でも子どもにとっての宝物になるのではないでしょうか。
まとめ:パパの歌は時代を超えて
忌野清志郎の「パパの歌」から現代のパパ像まで、父親の役割は時代とともに変化してきました。そしてこれからも変化していくでしょう。でも、清志郎が歌に込めた「いつでもそばにいる」という父親の愛情は普遍的な価値として残り続けています。
どんな職種においても「昼間のパパ」の姿は子どもに見せられないのが惜しいほど格好良いものです。もし見ることができたならば、どんなスーパーヒーローにも劣らないほど子どもの目には格好良く映るでしょう。
子どもが大きくなっても、いつでもそばにいる存在でありたい—それが一番大切なことかもしれません。形は変わっても、パパの愛情が子どもに届けば、それが最高の「パパの歌」になるのです。
あなたも、あなただけの「パパの歌」を子どもに届けてみませんか?